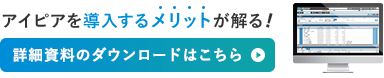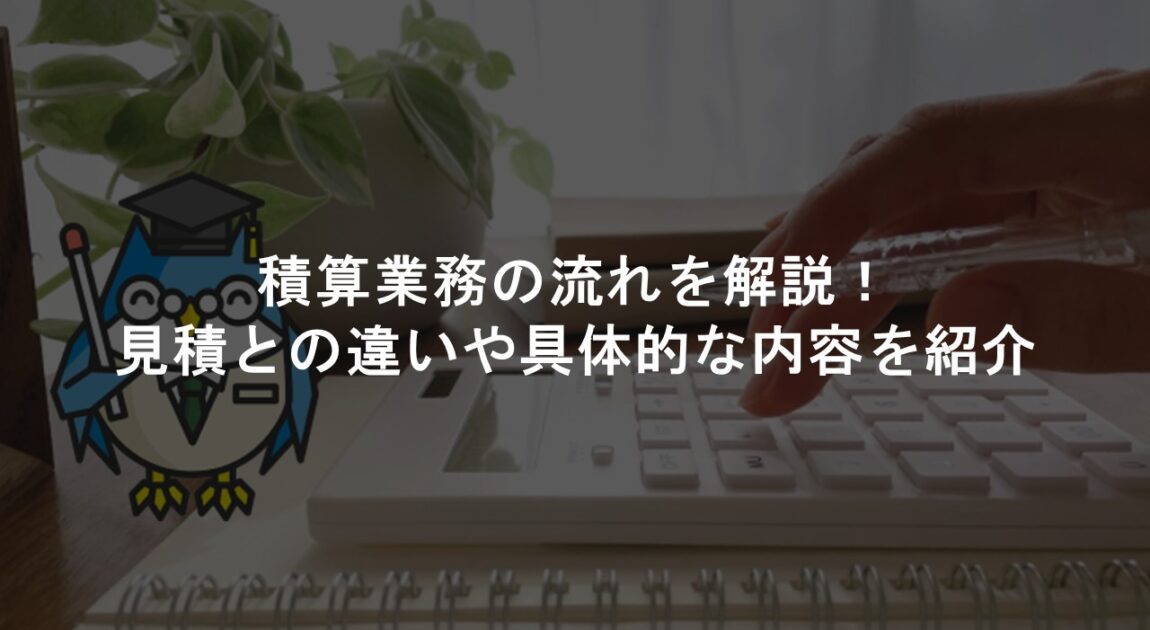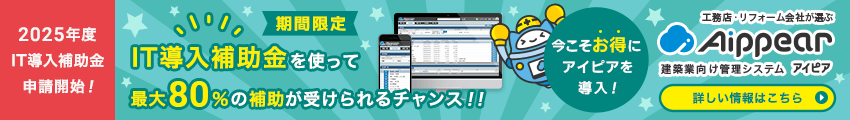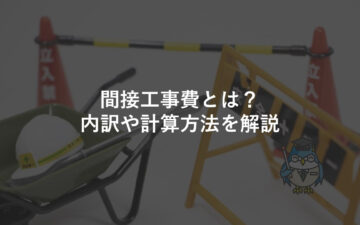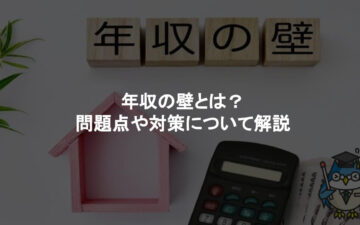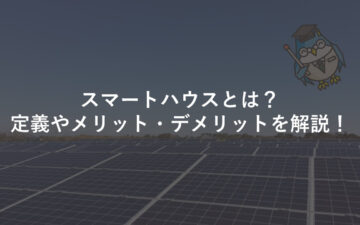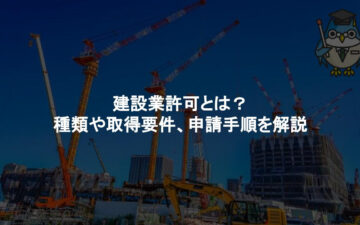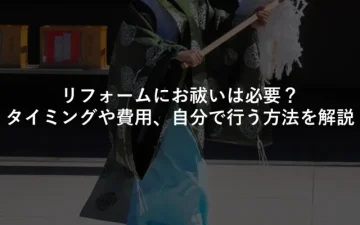積算は、工事全体にかかる費用をあらかじめ明確に割り出すという、重要な仕事です。
設計書や仕様書をもとに工事にかかる費用を一つひとつ積み上げていくことで算出し、事業利益に直結します。
図面の読み取りに始まり、相場や景気の予想も必要となることから、責任の大きな業務と言えます。
ここでは、積算業務の概要や流れを追いながら、見積との違い、必要なスキルや押さえておくべきポイントなどを詳しく解説します。
積算とは

積算は建築を行ううえで欠かせない業務です。
具体的には工事全体にかかる費用を明確にすることですが、その作業は一つひとつの工事にかかる費用の積み上げです。
設計図面や仕様書などの書類を正確に読み解き、予算を踏まえたうえで適切に材料や人材の必要量を算出する仕事となります。
もちろん、こうした数量は現場ごとにすべて変わるため、都度、現場に合わせた費用を算出する技術が必要です。
積算が甘いと、工事全体の進行に関わる大きな問題につながるおそれがあります。
たとえば、工事に取り掛かってから材料や人手不足が発覚すれば、追加による持ち出しで一気に赤字に転落するリスクもあります。
計算一つで企業が多大な損失を負いかねないとなれば、担う責任の重さは理解できるでしょう。
建築業では同じ建築物でも現場によって千差万別に変化するため、常に決まった原材料で決まった製品を量産するライン生産と同じというわけにはいきません。
すべて異なる現場の一つひとつを丁寧に読み解き、間違いのない数字を算出する重要な作業と言えます。
積算に関連する記事はこちら
積算と見積の違いとは
工事費用を算出するというと、見積を思い浮かべる人は多いでしょう。
一般では積算と見積が混同されがちですが、両社はまったく違うものなのでしっかり認識しておきましょう。
違いは以下の通り明確です。
- 積算:一つひとつの工事費用を積み上げたもの
- 見積:積算に利益を加えたもの
つまり、施工主などへ提出する見積を適切に作成するためには、まず正しい積算が欠かせません。
順番としては、以下の流れになります。
- 積算する
- 積算に利益を加算する
- 2を元に見積を作成する
仮に積算のまま施工主へ金額を提示してしまった場合、事業として利益が無い状態になります。
積算と見積の違いは、担当者はもちろん、経営者も明確に理解しておく必要があります。
積算と見積の違いに関する記事はこちら
積算の業務の流れ
積算業務の流れについてまとめていきましょう。
工事全体にかかる費用を漏れなく積み上げるためには、一つひとつの項目を正確に算出しなければなりません。
手間のかかる作業ですが、利益に直結する重要な項目ですので慎重に進めていきましょう。
細かい部分はありますが、大きく分けて全部で4つの工程があります。
必要な人材を算出
まず、工事にかかる人件費の算出から始めましょう。
人件費は工事費用の中でも、大きなウェイトを占める重要な項目です。
どういった人材がどこにどれだけ必要か、工事の仕様書を睨みながら施工条件を把握することから始めます。
明確にすべきなのは、必要とされる職種や資格者などが、どの工事にどれだけ必要とされるかです。
工法によっても都度変わりますし、環境条件によっても変化しますので、具体的な人数と、抱えておく必要がある日数を行程から算出します。
必要な材料を算出
人件費の次は、工事に必要な材料の算出に移ります。
設計図に沿って、どのような材料や設備がどれだけ必要か正確な量を算出しましょう。
材料の算出は、積算で最も漏れや抜けが出やすい項目です。
同じ建材でも工法が異なると必要量が大幅に変わることもあるため、慎重に進めなければなりません。
設計図や仕様書を読み込み、不明点があれば設計担当や施工担当に確認し、綿密に連携を取りながら進めることが重要です。
工事費用の算出
積算で重要となる『人』と『材料』の必要量が明確になったところで、いよいよ工事全体の費用を算出することができるようになります。
基本的にはそれぞれの『必要量×単価』で計算できますが、単価は工事によっても異なる部分が出てくるので注意しましょう。
参考資料としては、以下の資料などが使えます。
- 建設物価:一般財団法人 建設物価調査会
- 積算資料:一般財団法人 経済調査会
書類作成
最後は積算した数字を書類の体裁に整える作業です。
書類は施工主や取引先など、顧客と信頼関係を築くうえで非常に重要な存在です。
正確に作成するのはもちろんのこと、見やすく管理しやすいことが大切になってきます。
もし書類作成がよくわからず作業が進まないという場合は、有効なエクセルテンプレートを活用するのがおすすめです。
また、作成した書類は管理も大切ですが、データの整合性やセキュリティ面で問題を起こさないためには、クラウドシステムの活用が有効です。
テンプレートでより簡単に短時間で書類作成し、クラウドで一元管理することで業務効率化と情報集約を実現できます。
業務効率化に関連する記事はこちら
積算基準とは
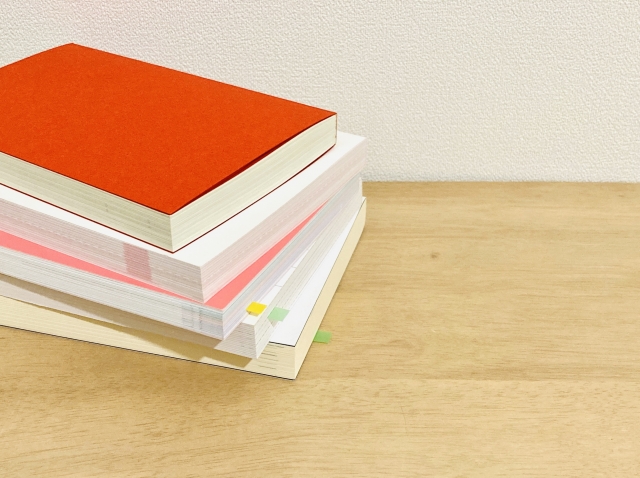
積算を効率的に進める時に役立つのが積算基準です。
積算基準とは、国土交通省が定める積算のルールブックのようなものであり、内容は工事費項目の定義や金額算定方法などが挙げられます。
そもそも積算に法的なルールはありませんが、先にも触れた通り工事書類は社会信用に直結する重要な存在です。
特に公共工事などでは見積の根拠が必須となるため、積算の裏付けとなる基準を設け、不正操作のおそれのない公平な見積を得るために活用されています。
この積算基準は公共工事だけでなく、一般工事にも使用することができます。
国土交通省の積算基準
国土交通省が監修する積算基準は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の『公共建築数量積算基準』です。
基本的に公共工事に活用されますが、一般工事にも使用することができます。
随時改訂されるため最新のものを参照する必要がありますが、項目は建築工事だけでなく、電気設備、機械設備、昇降機設備に分かれています。
また、国土交通省の公式サイトには『公共建築工事積算基準等資料』が公開されており、こちらは無料で利用できます。
- 国土交通省:公共建築数量積算基準
- 国土交通省:公共建築工事積算基準等資料
市販の書籍
国土交通省監修以外では、公共住宅事業者等連絡協議会等の監修による『公共住宅建築工事積算基準』があります。
その他各社が独自に基準を定めている場合もありますが、市販の書籍として販売されているのは国土交通省が定める積算基準です。
よく知られているものは以下の通りです。
その他基準に関連する記事はこちら
積算業務に必要なスキルは?
ここまで述べてきたように、積算は建設の事業に直結し、工事全体をも左右する重要な作業です。
基本的に必要なスキルは建築計算スキルですが、一人でできる仕事ではないため、コミュニケーションスキルも大切だと言えるでしょう。
さらに、正しく効率的に積算を行うためのスキルポイントは3点あります。
ポイント1
工程表を正確に作成するスキル
正しい施工計画を立てるスキルが必要です。
見積段階から具体的な工程表を作成することで、使用材料、使用機材、必要人員などが明確に算出できます。
ポイント2
環境条件を踏まえるスキル
気候、地形、季節などの環境条件も踏まえて対策を盛り込むスキルが必要です。
経験も重要ですが、設計図や仕様書からはわからない現場の状況は都度確認しましょう。
ポイント3
ツールを使いこなすスキル
人的ミスを極限まで減らすために、必要なツールを使いこなすスキルが必要です。
テンプレートやクラウドの必要性を書きましたが、入力ミスや確認漏れなどによる損失を避けるためにも必須のスキルです。
ITツールに関連する記事はこちら
資格はいるのか

積算業務に直結する資格は、民間資格の『建築積算士』です。
公共工事の入札ではこの資格が基準条件ですが、一般工事ではこの資格がなければならないというわけではありません。
ただ、重要な業務を遂行できる技術があることを証明する資格ですし、専門性が高いため挑戦する意義は大いにあります。
試験は一次試験(四肢択一式)、二次試験(短文記述、実技)があり、例年合格率は50~60%です。
より上位には『建築コスト管理士』、より下位には『建築積算士補』がありますが、いずれにしても専門性が非常に高く、現場未経験者が合格を目指すのは難しいでしょう。
経験者であれば独学でも可能ですが、確実性を狙うなら日本建築積算協会主催の講習会に参加するのが近道です。
建築積算士は必須資格ではないものの、積算の仕事に携わるなら一度は狙ってみるべき資格と言えるでしょう。
欲している企業は多いですし、転職にも年収アップにも有利になる期待があります。
積算の資格に関する記事はこちら
クラウド型見積ソフトなら『建築業向け管理システム アイピア』
まとめ
積算の流れや具体的な内容について紹介しました。
積算は建設業界にしかない専門性の高い業務であり、工事費用全体を明確にし、事業収益に直結する非常に重要な業務であると言えます。
ただし、工事に必要な人・物・金のすべてを明確に洗い出す仕事のため、決して簡単ではありません。
それだけに携わることには大きなやりがいを感じますし、身につければ大きな武器となるでしょう。
原価管理の基礎に関する記事
- 原価管理とは?メリットや効果的な管理方法をご紹介
- 原価計算とは?目的や計算方法を詳しく解説
- 原価管理をきちんと行うためのABC(活動基準原価計算)計算方法やメリットも解説
- 【リフォーム業界向け】原価計算書を作成して粗利率低下を防止