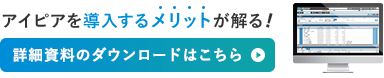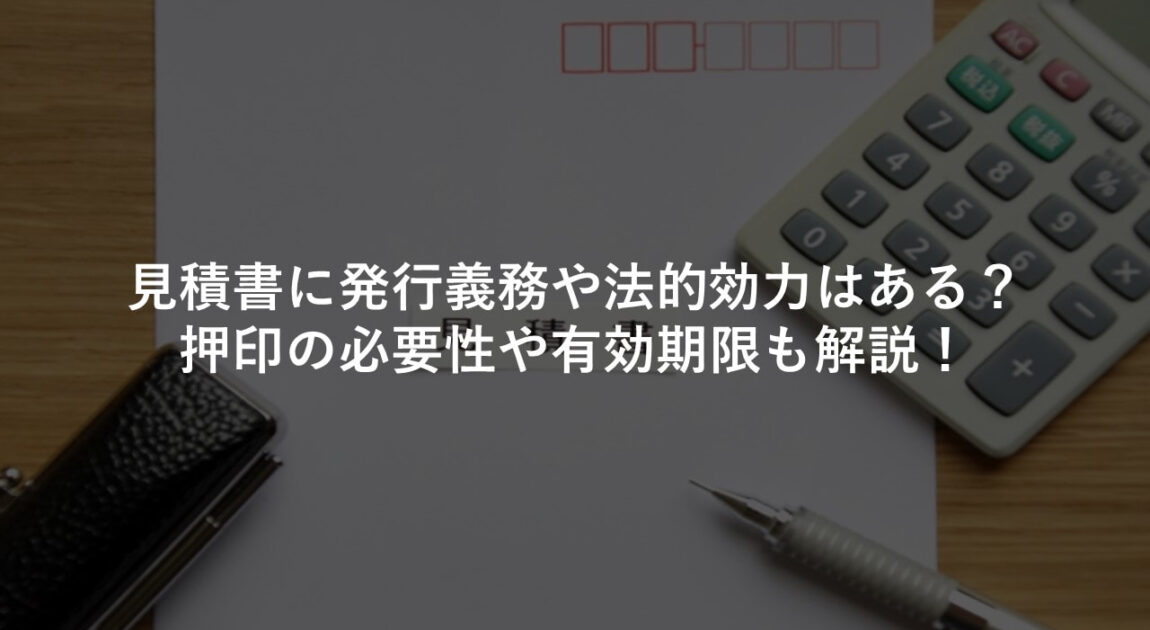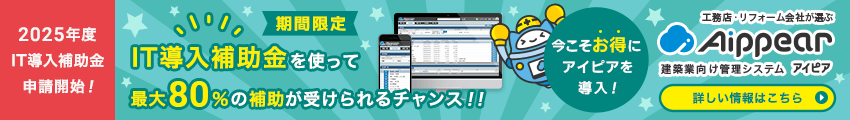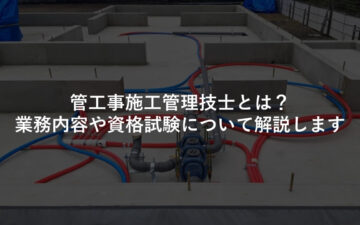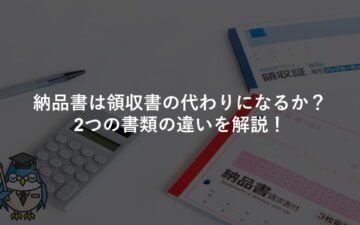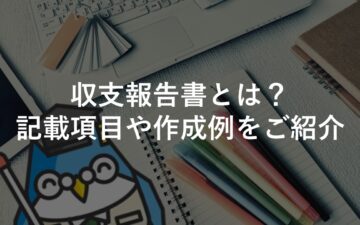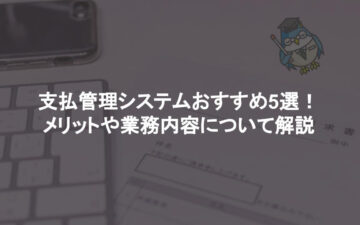商品やサービスを購入する際、どの程度の金額がかかるのかわからないと受け取る側も不安を感じます。
見積書を交わすことで、購入する前にどの程度の金額がかかるか確認できて安心です。
契約や購入前に交わす見積書には、発行される義務や法的な効力はあるのでしょうか。
こちらの記事では、発行義務や法的効力、有効期限はいつまでかについて解説していきます。
見積書の役割とは

必ず見積書を提出しなければいけないと義務化はされていません。
しかし、商品やサービスの取引を行う際には、見積書を交わしている業者がほとんどです。
決まりはなくても取引を行う際に、見積書を交わしているのにはさまざまな理由があります。
こちらでは、見積書がどのような役割を果たしているのか説明していきます
信頼性の確保
口約束だけをするよりも、見積書があると双方が安心です。
これから商品やサービスを利用する側にとって、いくらぐらいかかるのかわからないまま口約束だけで決めることは不安です。
見積書を提示すれば数字でいくらかかるのかわかり、信頼して頼めると感じやすくなります。
何も金額を提示するような書類がないままよりも、企業としても信頼を得ます。
適切なタイミングで見積書を提示できれば、商品やサービスを購入するまでスムーズに促せるでしょう。
特に企業では担当者だけでなく、会社全体で購入するかどうか決めます。
見積書があれば相手の企業全体に対しても信頼を与え、予算もイメージできるため、そのまま契約になりやすいです。
双方の認識の齟齬を防止
商品やサービスを購入する時、口だけで約束をしてしまうとお互い後からトラブルに発展してしまう可能性があります。
一緒に話をして相手に伝わったと思っていても、勘違いをして捉えているかもしれません。
見積書にだいたいいくらになるのか数字で表示されていると、客観的に捉えられます。
しかし、口で伝えてしまうと、相手は良い部分だけを聞いてしまい、もっと安い費用を想像しているかもしれません。
自社では伝えたつもりでも、相手は聞いていないとなりトラブルになってしまう可能性が十分にあります。
毎回ボイスレコーダーで一言一句録音しているわけではないため、証拠となる見積書が必要です。
話だけではイメージをしながら聞いてしまいますが、見積書があると数字として商品やサービスが購入できそうか見えてきます。
書面上で取引をしておけば、後から疑問が生じた時も双方で確認ができます。
うっかり忘れていた話も見積書の書面を見て思い出すことができれば、後々トラブルになりません。
取引が終わった後も、見積書は原則決算期の単位で7年後の法人税の申告期限日まで保管しなければならないと決まっています。
急に提示を求められても、すぐに出せるようにしておきましょう。
支払条件を伝える
見積書を提示することで、支払条件も一緒に伝えられます。
決して商品やサービスをプレゼントするわけではないため、支払条件を提示することは重要です。
企業ごとの資金繰りの関係からも、しっかりと明記しておきましょう。
特にいつまででも支払いを待っているわけではないことを示すために、期限は明確にする必要があります。
受注内容も1回の取引で終わりではなく、長期的にわたる場合もあるでしょう。
その際自社として経費の扱いをどうするのかも決めておく必要があります。
ほかには何の方法で支払いをOKにするかも、明記しなければなりません。
現金か指定金融機関への口座振り込みのみにするのか、小切手などの振り込みもOKにするのか記載します。
口座を明記する場合は、口座の種類が普通か当座かを忘れずに記載し、金融機関名、口座の種別、口座番号、口座名義(カタカナ表記)も載せます。
約束手形の支払いにする場合も、手形の支払期日をしっかりと記載しておきましょう。
見積書の法的効力
見積書は企業同士のやりとりで必要なものですが、法的効力があるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
こちらでは、詳しく見積書に法的効力があるのか見ていきます。
見積書に法的効力はあるのか

見積書には、法的効力はありません。
まだ実際に商品やサービスの代金を支払って購入している段階ではなく、あくまで検討している最中なため、必ず見積書を発行しなければならないという義務もありません。
企業同士法的効力はなくても、見積書があればスムーズな取引ができるとわかっていて商慣習上で発行されています。
ただ、何の意味もない書類でもありません。
見積書を発行にしているにもかかわらず、記載された内容を撤回してしまうのはダメです。
まだ契約を結んでいない段階でも、見積書に対して承諾があれば法律として契約は成立します。
そのため、トラブルを防ぐために見積書に有効期限を利用して法的効力に制限をかける場合もあります。
見積書への押印は必須なのか
見積書へ押印は絶対にしなければならない決まりはありません。
万が一押印がないとしても、法的効力が変わってしまうこともありません。
しかし、何もない状態よりも、社内でしっかりと検討された見積書だと示せます。
受け取った側としても、安心感や信頼感につながります。
何もない状態で見積書を提出するよりも好印象です。
見積書に押印する場合は、会社の角印と担当者印の両方が押されことが多いです。
電子化した見積書は有効か
見積書は絶対に紙でなければいけないわけではありません。
様式の決まりもないため、本来は自由です。
ただ、書かれている情報が少ない、肝心な部分の記載がないなど不備があると後からトラブルに発展してしまいます。
自社の信頼も失ってしまうので、注意が必要です。
電子化した場合でもまったく問題がなく、これまでの紙の見積書と同じ扱いです。
内容も特に問題がなければ、正式的な見積書となります。
見積書の書き方に関する記事はこちら
見積書の有効期限

一般的に見積書を見てみると、有効期限が記載されています。
双方のトラブルを防ぐためでもありますが、ほかにもさまざまな理由があります。
有効期限の目的
どの企業も簡単に取引をして購入すると決断できません。
企業にとって大切な予算を利用するため、じっくりと検討し本当に必要か話し合いがもたれます。
有効期限がないと、いつまでも見積書に書かれた内容で悩むことが可能です。
そのうち、他社と契約が決まってしまい、自社との話はなかったことにされてしまう可能性もあります。
有効期限があればそこまでに決めなければいけないため、早期に契約を促せます。
一般的な有効期限の期間
早く返事が欲しいからと、あまりにも期間が短いと企業の中で検討もできず、逆に断られてしまう可能性が出てきます。
一般的には2週間から6ヶ月の間で有効期限は設定されますので、この期間を参考にしながら設定すると良いでしょう。
有効期限を設定しておけば、過ぎた時はこの見積書の金額で提供しなくてもOKです。
将来、商品やサービスの価格を変更しなければならない時も出てくるかもしれません。
トラブルを回避するためにも、有効期限は重要です。
設定するうえでの注意点
実は民法の第523条の条文では、承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができないとあります。
自社の見積書を出す際には、なんとなくで設定してしまうのは危険です。
後からやっぱり有効期限を6ヶ月から1ヶ月に短縮したいと思っても、自由には撤回できません。
自社としても、有効期限を決める時には慎重にならなければなりません。
クラウド型見積ソフトなら『建築業向け管理システム アイピア』
まとめ
見積書は発行義務や法的効力があるかどうかという点ではどちらもありません。
様式なども決まっていないため、自由に記載もできます。
しかし、双方の認識のズレを解消し、購入までスムーズに促す書類でもあります。
適当にしてしまったら、後からトラブルに発展するため注意が必要です。
見積書は発注書などといった内容の承諾する書類と合わせれば、契約や取引内容の証明としても使えます。
発行する際は、有効期限を設定しておくと、さまざまなトラブルを回避できます。
有効期限については一度決めて見積書を発行したら変えられないため、漠然と決めるのはやめましょう。